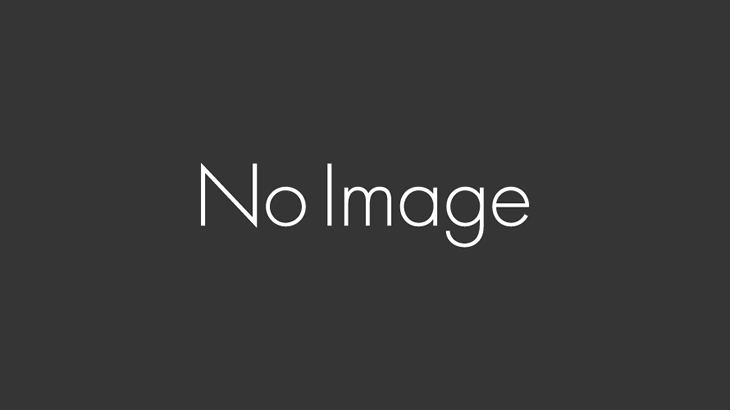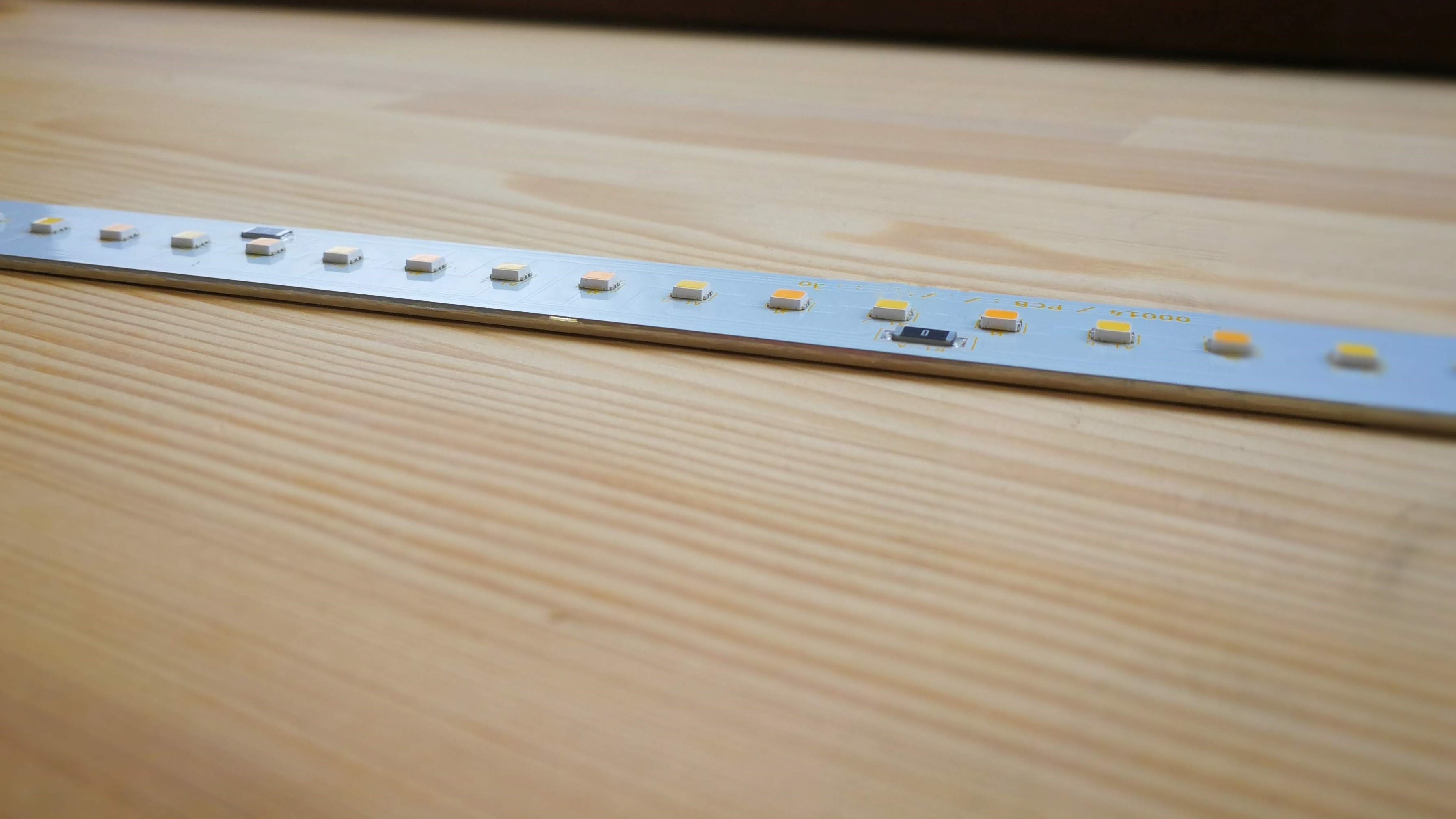世の中の変化に疎くて知りませんでしたが、光の色度の定義に新しいものがあったのですね。
一般に使われている色度の決め方は、CIE 1931 2°表色系と言うものですが、これに対してCIE 2015 10°と言うものがあるようです。
OSRAMさんのサイトを見て知りました。
網膜上の錐体の分光感度が2°の視野角と10°の視野角とで微妙に異なるそうで、この辺りを調整した測り方の様です。
確かにある程度の広い面積を見ている場合には10°の視野角で考えた方が合理的なのかも知れませんね。
仕事仲間と話しをしていた中では、美術品を眺める場合には、注目する対象がそれなりに小さなエリアを次々に見ていくことになるので、これまで通り2°の視野角での議論の方が適しているのではないか、との意見もあり、これはこれでそうかなと思ったりもします。
いずれにしても、光の質をある程度定量的に考える時にはその測り方も十分に検討すべき項目ですので、もっと勉強して正確に理解をしておかないとならないですね。
精進します。
目次